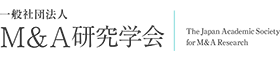設⽴趣旨書
中⼩企業・⼩規模事業者、⼤企業、スタートアップなど、あらゆる企業にとってM&A(合併・買収)を戦略的な選択肢として位置づけることの重要性が⾼まっている。
中⼩企業・⼩規模事業者は⽇本経済において重要な役割を果たしているが、経営者が⾼齢化する⼀⽅で、後継者難から事業の存続が危ぶまれている。また、事業の成熟化に伴い、収益性も低下してきており、ビジネスモデルの再構築を迫られている。こうした課題を解決するためには、ファミリー(⼀族)による事業承継だけではなく、第三者承継を円滑に実践するための仕組みを構築する必要がある。また、既存事業を持続的に成⻑させるとともに、将来の事業の柱となりうる新規事業の創出にも取り組む必要がある。そのための重要な戦略的な⼿段がM&Aである。つまり、中⼩企業・⼩規模事業者にとっては事業承継としてのM&Aだけでなく、既存事業の再構築(知の深化)のためのM&Aや、新規事業の展開(知の探索)のためのM&Aといった「両利きの経営」を視野に⼊れたM&Aが求められる。
また、M&Aを軸にした事業の集約化やイノベーションの創出を通じた⽣産性の向上の必要性は、中⼩企業・⼩規模事業者に限定されるものではなく、⼤企業にとっても同様である。上場企業の多くのPBR(株価純資産倍率)が1を下回っていることも指摘されており、事業ポートフォリオの再構築やM&Aを通じた成⻑戦略の遂⾏の重要性が⼀層⾼まってきている。
スタートアップについても、成⻑を遂げた新規公開企業(IPO企業)の多くが上場後に成⻑を失速させている。スタートアップ⽀援の議論においては、オーガニックグロース(⾃助努⼒での成⻑)を前提とすることが多く、企業買収や合併などM&Aを通じた他社資源をもとに⾃社の成⻑や企業価値の向上を促す⼿法としてのノン・オーガニックグロースの成⻑戦略や、そのための環境整備は⼗分ではない。持続的な成⻑が実現可能なIPO企業を創出するためには、グローバル市場への事業展開を模索するM&Aや、国内市場では圧倒的な市場占有率を⽬指すロールアップを⽬的としたM&A、競争⼒を⾼めるビジネスモデルの⼤幅な強化を⽬指すM&Aなどを促す必要がある。
このような多様なM&Aを促進するためには、実務家(当事者や⽀援者など)が経験に基づくノウハウを蓄積し、研究者が研究成果に基づく政策提⾔を⾏い、政策担当者が現場の声や学術的知⾒に基づき適切な政策を実施していく必要がある。こうした関係者が⼀堂に会し、M&Aに関わる様々な議論を深め、⽇本におけるM&Aの促進に貢献することを⽬的として、本学会を設⽴するものである。
2025年4⽉1⽇
設⽴発起⼈⼀同